睡眠薬の種類と強さが知りたい!ランキング付けできる?
睡眠薬には、病院で処方される「睡眠薬」とドラッグストアなど市販で購入できる「睡眠改善薬」があります。
睡眠薬は作用の仕方によってさらに3種類に、睡眠改善薬は成分の違いによって2種類に分類されます。
手元にある睡眠薬が他の薬と比べてどのくらい強いのか、副作用が強い薬なのかなど気になる方も多いのではないでしょうか?
この記事では、効果と副作用のバランスから、各睡眠薬の位置づけを解説しています。
睡眠薬は効果の強さよりも、自分の体質と不眠の症状に合った薬かどうかが大切です。薬の選び方についても詳しく紹介していますので、ご自身のお悩みに合った睡眠薬選びの参考にしてください。
- 睡眠薬にはどのような薬があるかが分かる
- 睡眠薬の効果と副作用の強弱が分かる
- 自分の不眠にはどの睡眠薬を選んだらよいかが分かる
- 睡眠薬を選ぶ時の注意点が分かる
睡眠薬を処方してくれるおすすめのオンライン診療は次の2つです。
| クリニック名 | デジタルクリニック | DMMオンラインクリニック※1 |
|---|---|---|
| クリニックロゴ |  | 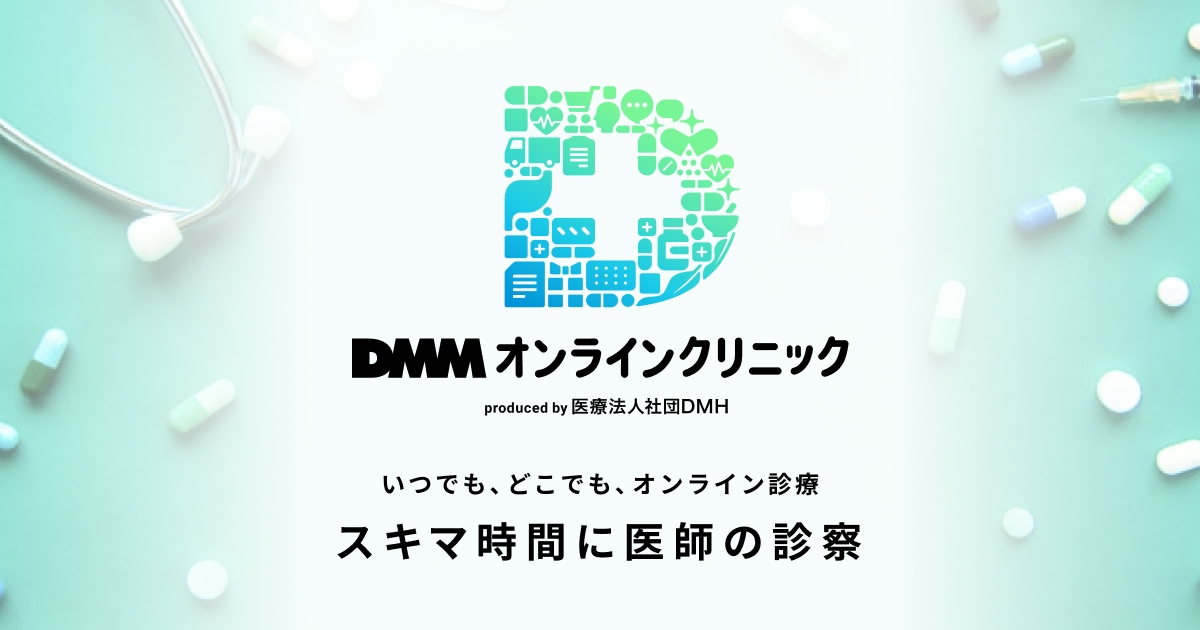 |
| 料金(デエビコ5mg) | 6,358円/月(税込) | 7,370円/月(税込) |
| 配送料 | 550円(税込) | 550円(税込) |
| 診察料 | 無料 ※クーポン適用必要 | 無料 |
| 料金総額 | 6,908円/月(税込) | 7,920円/月(税込) |
| 処方可能な薬 | ・エスゾピクロン ・ルネスタ ・リスミー ・デエビゴ ・ラメルテオン | ・エスゾピクロン ・リスミー ・デエビゴ ・ラメルテオン |
| 公式サイト |
※1 DMMオンラインクリニックはオンライン診療のプラットフォームサービスです。診療は提携先医療機関である、医療法人社団DMHが行っています。
睡眠薬で1番よく効く薬は何?
睡眠薬の効果は個人差が大きく、一概に「1番よく効く薬」を特定することはできません。
「眠れない」という症状は同じでも、寝つきが悪いのか、夜中に起きてしまうのか、昼夜逆転しているのか…などの悩みによって選ぶ薬が変わるためです。
不眠の症状に合った1番よく効く薬を選ぶために、まずは睡眠薬の種類について理解を深めましょう。
睡眠薬は病院で処方される「睡眠薬」とドラッグストアなど市販で購入できる「睡眠改善薬」に分かれます。
それぞれの薬の特徴を知り、自分に合う「1番よく効く薬」を見つけましょう。
睡眠を改善させる薬は大きく分けて2種類
睡眠を改善する薬は、医療用の「睡眠薬」と一般用医薬品(市販薬)の「睡眠改善薬」の2種類に大別されます。
医療用睡眠薬は脳に直接作用する薬です。作用する場所によって3種類に分かれます。
効果が強く即効性がありますが、依存や転倒の危険性もあるため、使用には医師の診断と処方が必要です。
睡眠改善薬は、アレルギーを抑える「抗ヒスタミン薬」が主成分のものと、漢方が主成分のものとがあります。
効果は医療用の睡眠薬に比べて穏やかで、医師の処方なしにドラッグストアなどで購入できます。
一時的な不眠で、病院に行くほどではないけれど、眠れないのをどうにかしたいという人には睡眠改善薬がおすすめです。気分の落ち込みなどの心理的負担があるという人には、効果の強い医療用の睡眠薬がよいでしょう。
病院でもらえる睡眠薬
病院でもらえる睡眠薬は、大きく3種類に分かれます。
- 脳の興奮を抑える薬(ベンゾジアゼピン/非ベンゾジアゼピン)
- 睡眠リズムを整える薬
- 覚醒状態を抑える薬
抱えている不眠のお悩みや、年齢などによって最適な薬を選択します。
| 不眠の悩み・年齢 | 選ぶ薬 |
|---|---|
| 寝つきが悪い、途中で起きてしまう | ・脳の興奮を抑える薬 (ベンゾジアゼピン/非ベンゾジアゼピン) ・覚醒状態を抑える薬 |
| 朝早くに目覚める | ・脳の興奮を抑える薬 (ベンゾジアゼピン/非ベンゾジアゼピン) |
| 昼夜逆転している | ・睡眠リズムを整える薬 |
| 高齢で転倒リスクがある | ・覚醒状態を抑える薬 |
市販で買える睡眠改善薬
一般用医薬品として販売される睡眠改善薬には2種類あります。
- 抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン)が主成分の薬
- 漢方薬
抗ヒスタミン薬は、鼻水やくしゃみなどのアレルギー症状を抑える薬です。副作用の眠気を誘う効果を利用し、睡眠を改善する薬として販売されています。
市販されている睡眠改善薬は主成分であるジフェンヒドラミンが同じ量入っていますので、効果に差はありません。
薬の形状(錠剤・カプセル)や価格、量などを選ぶ際の基準にするとよいでしょう。
漢方薬は、緑内障や前立腺肥大症、小児など、抗ヒスタミン配合薬を飲むのに注意が必要な人でも安心して飲むことができます。複合的な効果を持つため、更年期や神経の高ぶりなどが原因の不眠症状がある人にも相性のよい薬です。
睡眠薬と睡眠改善薬はどちらが強い?
睡眠薬と睡眠改善薬で効果を比較すると、睡眠薬の方が作用が強いです。
睡眠薬は脳の神経に直接働きかけて確実な睡眠効果をもたらすためです。
睡眠改善薬で効果が出る人もいますが、薬との相性の良さや「薬を飲んでいる」という安心感が効果に繋がっている可能性もあります。
- 飲むとフワーッとしてきて、目を瞑ると夢みたいな映像が浮かんでくる。寝れるのが分かって嬉しくなる
- 本当に寝付けなくて何年も困っていたのですが、飲んだらすんなり寝れるようになりました。
- 効き目はまぁあったと思います。寝付きがだいぶよかったです。目覚めもすっきりしてました。
- 初めて飲んでまもなく頭がもわ~んとしただけですぐ眠くならず、3時間くらいしてから少し眠くなり2時間程度眠れました。
ただし、睡眠薬は効果が強い分、副作用が現れやすいとも言えます。睡眠薬では翌日の眠気や短期間の記憶障害、悪夢などを訴える人もいます。
睡眠改善薬では、翌日の眠気、口の渇きなどの症状が出る場合があります。
- 薬を飲んだとき夢遊病になって物を持って帰ったり、夜中に料理を作り作ったものを食べ散らかしてました。
- 気持ち悪いぐらいの悪夢を見るし、ほぼ毎晩金縛りで辛かったです。
- 眠気は確かに強く来ます。でもそれと同時に鼻炎薬の効果として、口と喉と鼻が乾いてカラカラ。
- 飲んだ次の日、薬が抜け切れなかったようでデロンデロンに麻酔が残ったかのような高熱時のような頭の重さとふらふら感に襲われました。
不眠に長く悩んでいたり、うつ症状などを伴う場合は、医療機関を受診し、確実に効果が期待できる睡眠薬を選ぶとよいでしょう。
病院に行くほどではない、一時的な生活習慣の乱れなどで眠れていない場合は、睡眠改善薬を一度試してみてはいかがでしょうか?
副作用が現れた時は薬の量を減らす、薬を変更するなどの対応が必要になるため、医師や薬剤師に相談しましょう。
睡眠薬の強さとランキング
睡眠薬や睡眠改善薬を単純な「強さ」でランク付けすることは適切ではありませんが、効果と副作用の現れやすさをふまえて、あえてランク付けするとすると、上記のようになります。
※催眠作用を比較。効果の現れやすさには個人差があります。メラトニン受容体拮抗薬は睡眠リズムを調整する薬のため、除外。
ただし、睡眠薬は不眠の症状や生活パターン、持病の有無などを考慮して、一人ひとりに最適なものを選ぶのが基本です。
「ベンゾジアゼピン系の薬だから1番良い」とは限りません。また、薬の効果には個人差があることにも留意しましょう。
睡眠薬で強いとされているものは?
一般的に、睡眠薬のベンゾジアゼピン系・非ベンゾジアゼピン系の薬が睡眠作用は強いとされています。
副作用であるふらつきは、ベンゾジアゼピン系の薬の方が起こりやすいです。
代表的な薬を、作用時間の長さごとに紹介します。
| ベンゾジアゼピン系 | |
|---|---|
| 作用時間の長さ | 薬剤名(商品名) |
| 超短時間型 | トリアゾラム(ハルシオン) |
| 短時間型 | ブロチゾラム(レンドルミン) |
| 中時間型 | フルニトラゼパム(サイレース) |
| 長時間型 | クアゼパム(ドラール) |
| 非ベンゾジアゼピン系 | |
|---|---|
| 作用時間の長さ | 薬剤名(商品名) |
| 超短時間型 | ・ゾルピデム(マイスリー) ・ゾピクロン(アモバン) ・エスゾピクロン(ルネスタ) |
医療用睡眠薬の種類と選び方
睡眠薬の選び方は、どのような睡眠の課題を抱えているかによって異なるため、まずは自分がどのタイプの不眠なのかを確認しましょう。
- 寝つきが悪い
- 眠りの途中で起きてしまう
- 朝早く目覚める
- 昼夜逆転している
ご自身の睡眠での困りごとが何なのかを把握することが、睡眠薬選びの第一歩です。
医療用睡眠薬は、大きく分けて以下の3種類があります。
| 作用 | 分類 | 薬名 |
|---|---|---|
| 脳の興奮を抑える | ベンゾジアゼピン/非ベンゾジアゼピン系睡眠薬 (作用時間によってさらに超短時間、短時間、中間、長時間に分かれる) | ・ゾルピデム(マイスリー) ・ブロチゾラム(レンドルミン) など |
| 睡眠リズムを整える | メラトニン受容体作動薬 | ・ラメルテオン(ロゼレム) |
| 脳の覚醒を抑える | オレキシン受容体作動薬 | ・スボレキサント(ベルソムラ) ・レンボレキサント(デエビゴ) |
それぞれ持続時間や効果、副作用が異なります。薬ごとの特徴を把握して、ご自身の睡眠の悩みに1番合う薬を選びましょう。
睡眠薬|効果と持続時間の比較
睡眠薬の効果と持続時間、代表的な薬剤名と特徴を一覧にしました。
ベンゾジアゼピン(非ベンゾジアゼピン)系睡眠薬
効果が比較的現れやすい薬です。作用時間が長さによって4段階に分かれているため、不眠の状況に合わせた作用時間の長さの薬を選ぶとよいでしょう。
他の系統の薬に比べて転倒リスクや依存性リスク、短期記憶障害などの副作用が起こりやすい特徴があります。
| 分類 | 作用時間 | 代表的な薬剤名(商品名) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 超短時間型 | 2-4時間 | ・ゾルピデム(マイスリー) ・エスゾピクロン(ルネスタ) | ・効果発現が早い ・翌朝の眠気が少ない ・依存性が比較的低い |
| 短時間型 | 6-10時間 | ・エチゾラム(デパス) ・ブロチゾラム(レンドルミン) | ・続けて飲んでも蓄積は少ない ・翌朝の眠気が少ない |
| 中間型 | 12-24時間 | ・フルニトラゼパム(サイレース) ・エスタゾラム(ユーロジン) | ・入眠困難~中途覚醒、早朝覚醒まで対応できる ・翌日に残りやすいため、昼間の眠気やふらつきに注意 |
| 長時間型 | 24時間以上 | ・クアゼパム(ドラール) | ・早朝覚醒によい ・翌日に残りやすいため、昼間の眠気やふらつきに注意 |
睡眠リズムの調整、脳の覚醒を抑える睡眠薬
比較的マイルドな作用を持つ薬です。ラメルテオンは効果が現われるまでに時間がかかります。すぐに眠りたい人向けではなく、睡眠リズムを整えたい人におすすめです。
スボレキサントやレンボレキサントは、ベンゾジアゼピン/非ベンゾジアゼピン系と作用が異なり、転倒リスクが少ない特徴があります。高齢者の不眠におすすめの薬です。
効果が現われやすい一方で、悪夢を見るという特殊な副作用が問題になることがあります。
| 分類 | 代表的な薬剤名(商品名) | 特徴 |
|---|---|---|
| メラトニン受容体作動薬 | ・ラメルテオン(ロゼレム) | ・体内時計に作用・自然な眠りを促進 ・依存性や転倒の危険性が低い ・マイルドな効果 |
| オレキシン受容体拮抗薬 | ・スボレキサント(ベルソムラ) ・レンボレキサント(デエビゴ) | ・覚醒を抑える ・スボレキサントは副作用に悪夢を見ることがある ・レンボレキサントは効果発現が早く、入眠困難にも効果あり |
睡眠薬|症状別の薬の選び方
不眠のタイプによって、次のような目安で薬を選びましょう。
| 不眠のタイプ | 選ぶ薬 | 薬剤名 |
|---|---|---|
| 寝つきが悪い | ・超短時間型 ・短時間型 ・オレキシン受容体拮抗薬 | ・ゾルピデム(マイスリー) ・エスゾピクロン(ルネスタ) ・エチゾラム(デパス) ・ブロチゾラム(レンドルミン) ・スボレキサント(ベルソムラ) ・レンボレキサント(デエビゴ) |
| 途中で起きてしまう | ・中間型 ・オレキシン受容体作動薬 | ・フルニトラゼパム(サイレース) ・エスタゾラム(ユーロジン) ・スボレキサント(ベルソムラ) ・レンボレキサント(デエビゴ) |
| 十分に寝られず、朝早く目が覚める | ・長時間型 | ・クアゼパム(ドラール) |
| 睡眠リズムが乱れている | ・メラトニン受容体作動薬 | ・ラメルテオン(ロゼレム) |
高齢者は副作用が現われやすいため、転倒リスクのあるベンゾジアゼピン系の薬は極力避けるようにしましょう。
睡眠薬|症状に合う薬を処方してもらうための受診の方法
受診の際は以下のことを伝えると、医師が薬を処方する際の手助けになります。ご自身の不眠の状況を記録につけるなどすると、役立ちます。
- 不眠の困っている症状
(寝つきの悪さ、途中で起きてしまう、十分に寝られず、朝早く目覚める) - 日中の眠気や生活への影響
- 現在服用中の薬
- 生活習慣(仕事、運動、食事など)
- アルコールの摂取状況
- 過去の睡眠薬の使用経験
とくに、交代勤務の仕事に就いている人などは睡眠リズムが乱れやすいため、生活上の工夫なども併せて尋ねるとよいでしょう。
睡眠薬|注意すべき副作用と対策
睡眠薬の主な副作用には、薬を飲んでからすぐに注意が必要なものと、翌日への影響、長時間服用することによる影響があります。それぞれの注意すべき症状と対策について紹介します。
| 注意が必要な時期 | 症状 |
|---|---|
| すぐに注意が必要 | ・ふらつき、転倒・短期記憶の欠如 ・判断力の低下 |
| 翌日への影響 | ・翌日の眠気 ・集中力低下 |
| 長期間服用による影響 | ・精神的/身体的依存 ・休薬時の症状悪化 |
このような副作用を避けるための対策として以下のものがあります。
- 睡眠薬は寝る直前に決められた量を飲む
- アルコールと睡眠薬を一緒に飲まない
- 定期的に医師の診察を受け、状況を相談する
- 急な服用中止を避ける
- 高齢者は低用量から開始する
注意すべき副作用を理解し、効果と副作用のバランスをみながら上手に睡眠薬を使用しましょう。
市販の睡眠改善薬の種類と選び方
睡眠改善薬には抗ヒスタミン薬を主成分とするものと、漢方を主成分とするものがあります。
抗ヒスタミン薬はジフェンヒドラミンという成分の副作用である「眠気」を応用して眠りを誘う薬です。
一方、漢方を主成分とするものは抑肝散(よくかんさん)という配合のもので、神経の高ぶりやイライラを鎮める作用も併せ持ちます。
薬を選ぶ際は、次のポイントを意識して選ぶとよいでしょう。
- 年齢
- 妊娠の有無
- 前立腺肥大、緑内障の有無
基本的に市販の抗ヒスタミン薬が主成分の睡眠改善薬は15歳未満の小児と妊婦さんは使用できません。また、前立腺肥大や緑内障を悪化させる可能性があるため避けた方がよいでしょう。
漢方を主成分とするものは、不眠以外の症状も改善させるため、イライラ、不安などの症状をあわせもつ不眠の方におすすめです。
睡眠改善薬|成分と特徴の比較
1.抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミン)を主成分とする薬
すべてジフェンヒドラミンが同じ量配合されているため、効果に変わりはありません。
薬の形やサイズ、配合成分、数量を比較し、1番合うものを選ぶとよいでしょう。
ドラッグストアや薬局など市販の店で購入できますが、安全のために薬剤師または登録販売者からの説明を受けての購入がおすすめです。
| 商品名 | 特徴 | メーカー希望小売価格 |
|---|---|---|
| ドリエル | ・錠剤タイプ ・1回2錠 ・3日分と6日分の販売形式あり | 1,100円(税込)/3日分 2,090円(税込)/6日分 |
| ドリエルEX | ・溶けやすいカプセルタイプ ・1回1カプセル ・ラベンダーアロマ配合 | 2,420円(税込)/6日分 |
| ネオデイ | 錠剤が小粒(直径7mm)で飲みやすい | 923円(税込)/3日分 |
2.漢方を主成分とする薬
漢方を主成分とし、比較的安全に使用できる薬です。更年期やストレスなどの症状を抱える不眠にも効果的です。
ジフェンヒドラミン含有の薬と同様、購入の際は薬剤師もしくは登録販売者からの積極的な説明が推奨されています。
| 商品名 | 特徴 | 価格 |
|---|---|---|
| スリーピンα | ・7種類の漢方を配合 ・ストレスや自律神経の乱れからくる不眠に ・更年期、シニア世代にも使用可能 ・1回4錠 1日3回 食前または食間 | 913円(税込)/2日分 |
睡眠改善薬|症状別薬の選び方
自然に近い眠りを求める方は、ジフェンヒドラミン配合の薬を選びましょう。ただし、購入の前に以下の3つのポイントを確認しましょう。
| 年齢 | ・15歳未満は服用できません。 ・高齢者は医師へ相談しましょう。 |
|---|---|
| 妊娠の有無、授乳中 | ・妊娠または妊娠の可能性のある方は服用できません。 ・授乳中の方も服用しないか、授乳を避けてください。 |
| 前立腺肥大、緑内障の有無 | ・前立腺肥大、緑内障がある方は症状が悪化する可能性があるため、医師へ相談が必要です。 |
これらの条件に問題がない場合は、ジフェンヒドラミン配合の薬の中から、飲みやすさや価格などを考慮して選ぶとよいでしょう。
スリーピンαは、漢方が主成分であるため、上記の条件があって飲めない人でも服用できます。
- 5歳以上の小児
- 前立腺肥大症、緑内障の持病がある
- 高齢者
上記の方は漢方をメインとする薬を試してみるのもよいでしょう。
漢方は複合的に症状を抑えるため、不眠にくわえて次の症状がある方にもおすすめです。
- 更年期で眠れなくなった
- 神経の高ぶりや不安で眠れない
- 小児の夜泣き
睡眠改善薬|注意すべき副作用
使用を控える、もしくは医師や薬剤師に相談が必要な人を表にまとめました。持病を悪化させてしまう可能性や、副作用が現れる可能性があります。
ジフェンヒドラミン配合薬
| 禁忌(薬を飲んではいけない人) | ・妊婦または妊娠の可能性がある人 ・15歳未満の小児 ・日常的に不眠の人 ・不眠症の診断を受けた人 ・併用できない薬(他の催眠鎮静薬、解熱鎮痛剤など) ・授乳中の人(服用中は授乳を避ける) |
|---|---|
| 服用後の注意 | ・服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。) ・服用前後は飲酒しない ・連用しない |
| 薬を飲むのに注意すべき人 | ・治療中の病気がある ・高齢者 ・アレルギーを起こしたことがある ・排尿困難 ・前立腺肥大症 ・緑内障 |
| 一般的な副作用 | ・下痢 ・口の渇き |
漢方配合の薬
| 薬を飲むのに注意すべき人 | ・治療中の病気がある ・妊婦または妊娠の可能性がある人 ・胃腸の弱い人 ・アレルギーを起こしたことがある |
|---|---|
| 一般的な副作用 | ・発疹、発赤 ・かゆみ |
睡眠薬に頼らない不眠への対策
睡眠薬や睡眠改善薬に頼らずに、よりよい睡眠のための生活習慣の工夫を紹介します。
具体的には睡眠環境の整備、生活リズムの調整、食事や運動に気を配ることで、眠りやすくなります。
不眠が続いたり、不眠のために日中の活動に支障が出るようであれば専門医を受診することも検討しましょう。
睡眠を促す生活習慣の改善
睡眠環境、生活リズム、食事や運動の観点からよりよい睡眠のためのアクションを紹介します。できることから始めてみましょう。
| 生活習慣 | 具体的な行動 |
|---|---|
| 睡眠環境の整備 | ・寝る前のスマートフォンやタブレット機器の使用を避ける |
| 生活リズムの調整 | ・毎日同じ時間に起床する ・日光を浴びて体内時計を整える ・夜更かしを避ける ・休日も平日と同じリズムで過ごす ・寝る1~2時間前にお風呂に入る |
| 食事と運動管理 | ・夕食は寝る3時間前までにすませる ・カフェイン摂取は午後3時以降は控える ・日中に適度な運動をする ・寝る前の激しい運動は避ける |
不眠にお悩みなら|専門医への相談タイミング
不眠の裏に、他の病気が隠れていることがあります。また、不眠が続くとメンタルも不安定になり生活の質が落ちるため、以下の症状がある場合は早めの受診をおすすめします。
かかりつけの内科医を受診し、不眠の原因に何らかの疾患が関わっている場合は専門医を紹介してもらいましょう。
- 1か月以上不眠が続く
- 日中の眠気で仕事や生活に支障が出る
- いびきや睡眠時無呼吸を家族に指摘された
- 極端な遅寝遅起きのため、学校や仕事に遅刻するなどして社会生活に支障を来たしている
- 市販の睡眠改善薬では改善が見られない
まとめ|睡眠薬の特徴を理解し、自分に合う薬を選ぼう
睡眠薬の種類は大きく分けて医療用睡眠薬と、市販で購入できる睡眠改善薬とがあります。効果としては医療用の睡眠薬の方が催眠作用は強いです。
睡眠薬の中で1番強い薬や、強さのランキング付けは難しいといえますが、ベンゾジアゼピン系の薬が効果や副作用が強い傾向にあります。
睡眠薬の強さだけでなく、不眠の症状や生活スタイルに合わせて、適切な睡眠薬や睡眠改善薬を選択することが大切です。
不眠でお悩みの方は一人で抱え込まず、専門家に相談することをおすすめします。
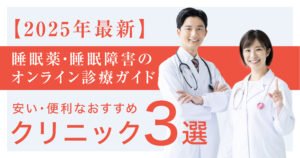


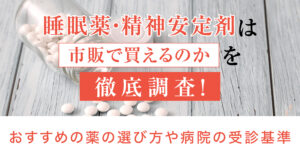
コメント